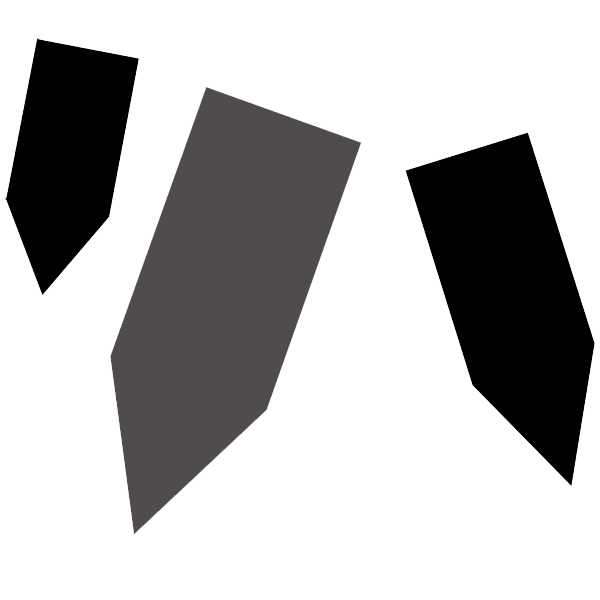最新の研究により、怒りがクリエイティブなパフォーマンスの向上と関連していることが分かってきました。
この記事を見てまっさきに思い浮かんだのは、少し前に流行りまくったアンガーマネジメント。
キンドルの自己啓発系はこれ関連の本ばかりでした。
マルチと新興宗教と自己啓発が苦手な自分は嫌悪感を隠せないので、そもそも近づかないようにしてるのですが、トレンドになるものはしばらく時間を置くとカウンターみたいな立ち位置の研究結果が出るのが常なので、今回もやっぱりな!というのが本音です。
でもね、怒りをコントロールするとか平和にみんな仲良く世界中大好き、みたいなのはどうも胡散臭く感じてしまって…
なにひとつ悪くないのですが、善良を恥じない姿勢には穿った見方をしてしまいます。
Facebook(現Meta)を作ったマーク・ザッカーバーグを描いたデヴィッド・フィンチャー「ソーシャル・ネットワーク」でも、女のコに振られた腹いせにハーバードの女子寮名簿をハッキング、女子をランキングしたサイト『フェイススマッシュ』を立ち上げ、アクセス集中により大学のサーバーがダウンするほどウケた理由を分析したのがそもそものきっかけ。
Netflix「プレイリスト」でも優秀なプログラマーでありながら、大卒資格がないためGoogleの採用試験に落ちたダニエル・エクの鬱屈が、Spotifyを一大産業にした一因として描かれています。
どちらの作品もフィクションなので、描かれているすべてが事実ではないにせよ、彼らの力の源のひとつに捩れまくった劣等感と反発心があったことは容易に想像できます。
それぞれジェシー・アイゼンバーグとエドウィン・エンドレの演技力もあってか、ふたりとも人間的な魅力を感じないクズとして描かれる一方、時代にマッチした革新性あふれる情報インフラを世界規模で展開する大企業を作り上げた天才です。
自分は作品や創作物そのものにしかあまり興味はなく、クリエイションの過程やクリエイターの人柄はかなりどうでも良い方なのですが、それでも人格破綻した性格の悪い者が素晴らしい芸術作品を作り出すアンビバレンツには惹かれます。
学生時代、周りが角川映画とかアイドルのファンムービーを観ているなか、ダリオ・アルジェントやジョン・カーペンター、クローネンバーグばかり観ていたせいでしょうか。
ちなみにウチの妹も「猟奇的要素がない作品は観てられない」といってます。
冒頭の研究発表を受けて、遠からず「怒りは抑えるな!」みたいな本が並ぶと思いますが、やはりまったく食指が動く気がせず読むことはないでしょう。
やっぱり自己啓発とふわスピがニガテなのです。
サブスクといえば地味に値上げしたNetflixですが、「ナイト・エージェント」2期が始まったのと、とにかくエマ・マイヤーズが可愛い「自由研究には向かない殺人」が観られること、そして「ウェンズデー」2期(エマ・マイヤーズも出てます)がアナウンスされたので当分やめられなくなりました。